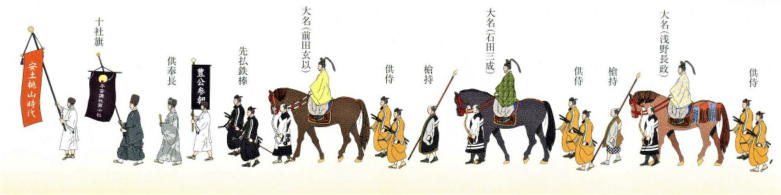�� �] �� �� �� �� |
�n�@�� |
���@�� |
�n�@�� |
�T�@�@�@�@�v |
�� |
���@�� |
������ |
���哰 |
1641�N |
�@�R����j�������ߓ���ƍN�̂��Ƃ𗣂�A�̂��ɕ���O���� ���� �����ΐ��R���������B �@���哰�̖��́A����T�H�炪�`���������O�\�Z����̏ё��� �ɁA�ΐ��R�����ꂼ��̎��l�̎��������A�����̊z���f�� �@������������v�̊ԁ��ɗR������B |
�� �g�t �~ ���� |
�o�X�� �u����� ���菼�v ��5�� |
�V |
�@�R�@ |
1680�N |
�@�@�R����q�̏Z�@�E���y�ƂƂ��Ɂu����ɕ��v���]������ �@�������ՂɌ��Ă�ꂽ�B �@�㐼�V�c�̍c���̌�������ڂ�������ł́A���G14�ʁi�d���j �@��������B �@�{���͏t�G�E�H�G�́����ʌ��J�����̂ݔq�ω\�B |
�g�t �~ |
�o�X�� �u��c���v ��4�� |
�V |
�@�؎� |
�@���Ƃ��Ƌ��s�w���߂ɂ��������̂��A1662�N�ɉ���O�c�˂� �@�ƘV�A���}�ߋ`�����̒n�Ɉڂ��V��@�̎��Ƃ��čċ������� �@�́B �@�{���͎߉ޔ@���B �@�{���E���O�E��ˉ��`�͈ڒz�����̂��́B �@�r���V���뉀�́A�ΐ��R����T�H�Ȃǂ����͂��č�� �@�����Ɠ`�����A�g�t�̃V�[�Y���ɂ͂��Ƃɔ������B |
�g�t |
�����d�S �u�O� ���v ��10�� |
|
�V |
�C�w�@ ���@�{ |
1659�N |
�@�㐅�����c�����s�s�̖k���ɑ��c�����L��� �R���B �@��̒����ɂ���u�_���v����͋��s�̎s�X����]�o���A �@�C�w�@���{���\�����i�̏ꏊ�B |
�g�t |
�o�X�� �u�C�w�@ ���{�O�v ��7�� |
���R�� |
���䎛 |
1605�N |
�@�L�b�G�g�̕������߁A�k�����˂˂�����ƍN�̔�� �@�đn���B �@���т��щЂɑ��������A�n�������̌����Ƃ��āu�J�R���v �@�u�P���v�u���J���v�u�\��u�ό���v�Ȃǂ��c��A��������� �@�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B |
�� �g�t �� |
�o�X�� �u���R�� ��v ��5�� |
������ |
���E��Y ����� |
1603�N |
�@����ƍN���㗌���鎞�̏h���Ƃ��đ��c�B �@���~�̐w�E�Ă̐w�ɂ́A����R�̖{�w�ƂȂ����B �@�c��3�N�i1867�N�j10�����吭��ҁ��ɂ���ė��j�̕���� �@���Ă̖�ڂ��I�����B |
�� |
�n���S �u����� �O�v ���� |
�E���� |
���`�� |
1686�N |
�@�����m�Ԃ̖剺�Ŕm�ԏ\�N�ɐ���������䋎�����ӔN���� �@�����������B �@�m�Ԃ�17���ԑ؍݂���������L�����L�����ꏊ�ł��m����B �@�u���`�Ɂv�̖��́A��̊`�낤�Ƃ��āA��ɑ������ �@���Ă����̂ɁA���̖�́u�앪�i�̂킯�j�v�Ŋ`�̎����S�� �@�����Ă��܂��A�߂ޖ��������ԋ������Ƃ����G�s�\�[�h�ɂ� �@�� �B |
�o�X�� �u���� ���w�Z�O�v ��6�� |
|
������ |
�j���{ |
1662�N |
�@���s�̐����A�j��̒����搼�݂ɉc�܂ꂽ���{�B �@�����{�Ƃ̏���q�m�e���ƁA���q���e�����q�ɂ���āA��5�N �@�ɂ���ԑ��c�ɂ���Ċ����������́B �@���̒뉀���L���ɂȂ����̂́A�h�C�c�̌��z�ƃu���[�m�E�^�E �@�g�����{���z�̐��E�I��Ձv�u�i���Ȃ���́��j���{�v�� �@��^���Ă���̂��ƁB |
�g�t |
�o�X�� �u�j���{ �O�v ��8�� |
������ |
���{�莛 |
1602�N |
�@����ƍN���{�莛�̗͂��킮���ߋ��@�Ɏ��n��^���{�莛���� �@���������āu���{�莛�v�Ƃ����B �@���s�̐l�X����́��������ƌĂ�Đe���܂�Ă���B �@�����̒����Ɍ���e���͐��E�ő勉�̖ؑ����z�B �@�����ɂ͏�y�@�̊J�c�A�e�a��l�̑������u����Ă���B |
JR �u���s�v ��7�� |
|
�F���s |
�ݕ��� |
1661�N |
�@���@�@�̑��{�R�B �@��������̓n���m�ł������B���T�t���A�㐅���V�c�̕ꁃ���a �@��@���̕ʑ��Ղɑn���B �@�@���i�J�育�Ɓj�͂��Ƃ��A�H����@�Ȃǂ������ɒ����m�@ �@�̓`�����p���ł���B �@���͂̓����ł́h���������h����Ă���B |
JR �u���@�v ��5�� |
���y�[�W�@�������� |